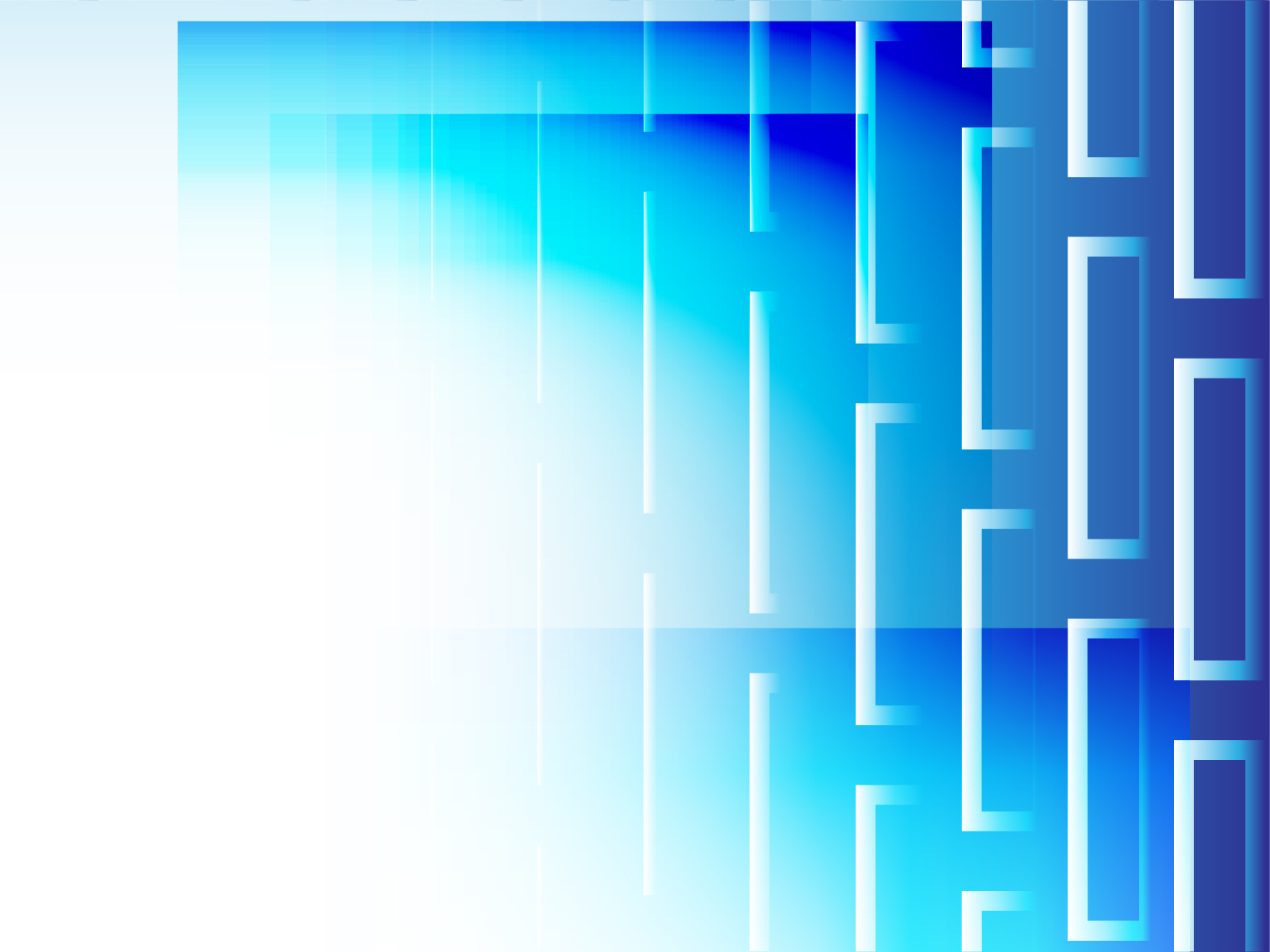思い出をたどる散歩
大学を卒業してしばらく経った頃、ふと学生時代を過ごした街を歩いてみたくなる瞬間がある。
それは必ずしも順風満帆な時とは限らない。社会人として思うようにいかず、足元が少しぐらついている時かもしれないし、あるいは結婚という人生の節目を前に、「自分はどこから来たのか」を確かめたくなる衝動なのかもしれない。
「右左見渡しても今はもう知らない顔ばかりで」「面影」「一人で歩く」という歌詞は卒業後、大学生活の充足した記憶がまだ残り香のように残っている20代後半という設定だろうか。少なくとも「今はもう知らない顔ばかり」という部分から4年程度は経過していることが想像できる。
その思い出をたどる散歩は、確かめたい何かを求めての行動であり、静かなる衝動だ。
舞台は「吉祥寺」
幾田りらの「吉祥寺」は、そんな“原点回帰の衝動”をやさしく肯定してくれる一曲だ。
曲の舞台は、その名の通り吉祥寺。
電車のホーム、今でも覚えている駅メロ、七井橋、池のボート、何気なく腰を下ろしたベンチ。歌詞に並ぶのは、観光地としての吉祥寺ではなく、日々の生活の中に溶け込んでいた風景だ。だからこそ、この曲は特定の街の歌でありながら、聴き手それぞれの「かつての居場所」と自然に重なっていく。
新海誠の描く東京の風景や世界観と重なるのは記憶の糸口に「駅」を置いているからだろう。「いつ振りかのOrangeLine」はまさに中央線であり、東京西部の「通勤電車」と「駅」というのは学生生活の「縁語」的な働きをする言葉でもある。「小田急」「東急」「京王」を風景に描くだけで、青春を喚起させる。「東武」や「京成」ではその色彩や味わいは出てこない。
人生のページをめくる前に立ち止まりたいとき、寄り添ってくれる一曲
「偶然、会えないかな」
その淡い期待は、特定の誰かに向けられているようでいて、実は過去の自分自身に向けられているようにも聴こえる。あの頃の自分は、今の自分をどう見るだろうか——そんな問いが、メロディの隙間からそっと立ち上がる。
この楽曲を聴いていて思い出されるのが、小沢健二の「いちょう並木のセレナーデ」だ。
どちらも、大学生活という人生の一時代を静かに振り返る、「大学生活振り返り系ソング」と呼びたくなる立ち位置にある。青春を美化しすぎることも、過度に切り取ることもなく、時間が経ったからこそ見える距離感で、かつての自分を見つめ直す。その温度感が、驚くほど似ている。
脱線するが、「いちょう並木のセレナーデ」は青春群像ドキュメンタリーのテーマソングにぴったりだ。「ザ・ノンフィクション」のエンディングにしてもよいと自分的には思っている。
そして、「吉祥寺」という曲を決定的なものにしているのが、幾田りらの歌声だ。それは、掌から零れ落ちる雫のように、掴もうとした瞬間にすり抜けていく透明感を持っている。強く主張するわけでも、感情を押しつけるわけでもない。それでも一度耳に残ると、郷愁だけが静かに、しかし確実に積もっていく。
この曲は、過去を懐かしむためだけの歌ではない。
今を生きることに少し疲れたとき、あるいは人生のページをめくる前に立ち止まりたいときに、そっと背中を預けられる場所のような存在だ。
幾田にとって「吉祥寺」を歩くことは、思い出をなぞる行為であり、同時に自分を確かめ直す行為でもある。そして、人それぞれ「吉祥寺」のような街は存在している。
――この曲は、ふとした瞬間に聴きたくなる。秋口の静かな日。香ばしい青春時代の思い出をなんとなくたどりたくなるときに、ぴったりな一曲だ。幾田の歌声は心に積もった澱を洗い流すかのように寄り添ってくれるだろう。