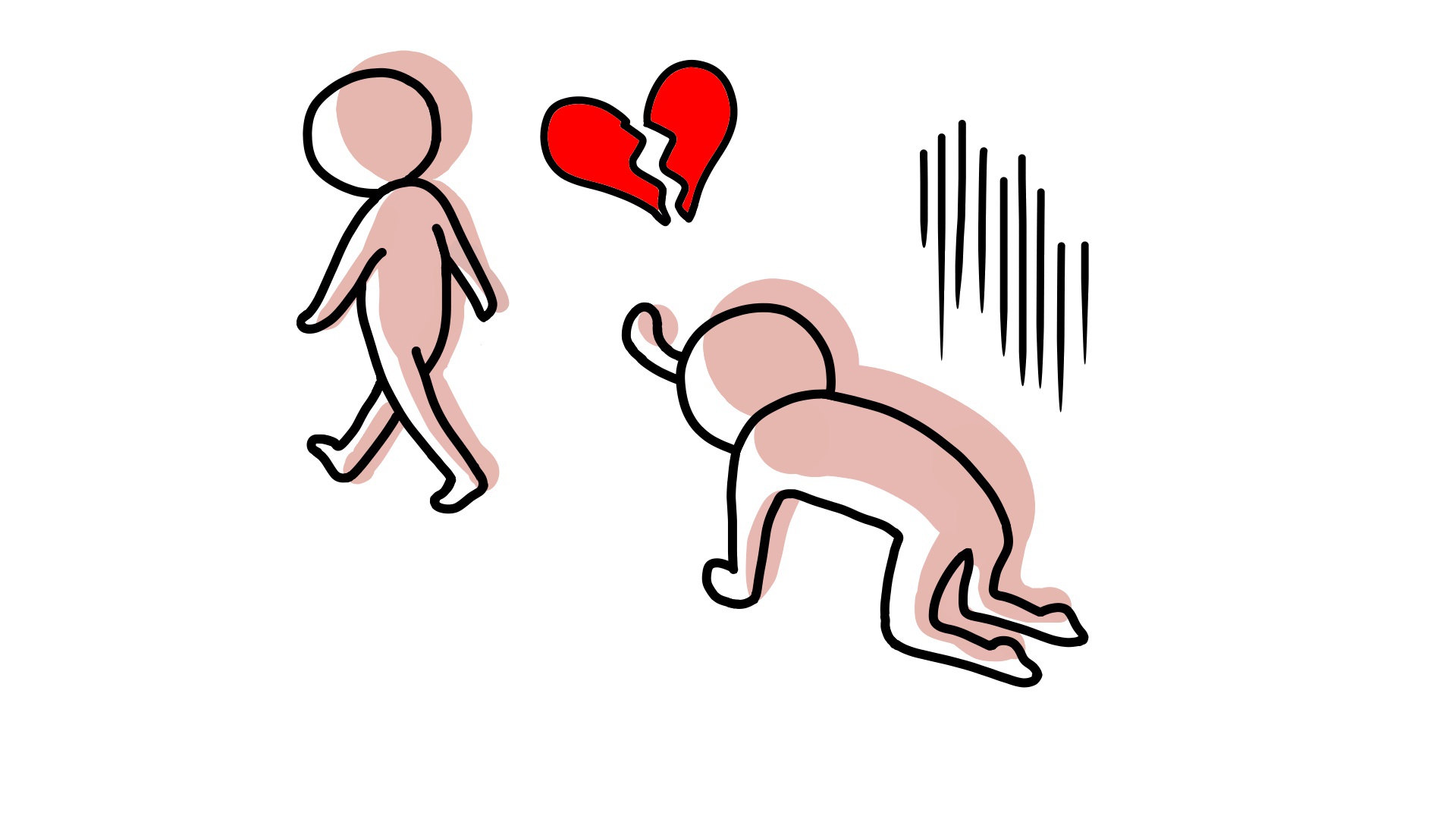静かな光を放つラブソング
幾田りらの「レンズ」は、彼女のソロ楽曲の中でもひときわ静かな光を放つ一曲だ。YOASOBIで見せる物語性の強いドラマとは異なり、この楽曲は、ごく個人的で、まだ言葉になりきらない感情を、そっとすくい上げるようにして描いている。
「かざしたレンズのその先に
ただ貴方がそこにいれば
華やいでいく心がここにあって」
ここで描かれるのは、風景ではなく“あなたがそこにいること”そのものだ。特別な場所でも、劇的な出来事でもない。ただ、あなたが視界に入るだけで、世界の色が少し変わる。このささやかな感情の動きを、過不足なく言葉にしてしまうところが、平安歌人ならぬ“令和の歌人”としての幾田りらの面目躍如である。
レンズという比喩が描く、片思いの距離
この曲に登場するモチーフは、カメラ、レンズ、ピント。だがそれは機材だけの話ではない。レンズとは、“あなたを見るための距離”を象徴する装置だ。近づきすぎず、しかし確かに捉えたい。その微妙な隔たりこそが、片思いの本質であり、幾田りらはそれを「カメラ」という比喩で描き切っている。
メロディーもまた、この距離感をなぞるように、静かで上品だ。感情を爆発させるのではなく、そっと置いていく。その上で、幾田りらの少し切なさを帯びた声が、リスナーの胸をじわりと締めつける。聴く側は、いつのまにか自分自身の片思いの記憶を呼び起こされてしまう。
瞳の真ん中に映るのは誰か――願いと不安の交差
「貴方が瞳の真ん中に映すのは誰なのかな?」
ここでレンズは、カメラから“瞳”へと置き換わる。私はあなたを見ている。では、あなたは誰を見ているのか。この一行には、「自分であってほしい」という願いと、「そうじゃないかもしれない」という不安が同時に詰め込まれている。疑問形で投げかけることで、その揺らぎがいっそう際立つ。前半で示された“カメラのレンズ”というモチーフが、ここで“瞳のレンズ”へと変換される構造も見事だ。
ラストの
「いつか二人寄り添い笑う日々がアルバムを彩れるように」
という一節では、再び写真の語彙が回収される。今はまだレンズ越しの関係でも、いつかそれが“二人の思い出”としてアルバムに並ぶかもしれない。その未来を断言せず、願いとしてそっと差し出すところにも、幾田りらの繊細な感性がにじむ。
「レンズ」は、恋の成就も失恋も描かない。ただ、誰かを静かに見つめてしまった、その瞬間の心のピントだけを合わせた歌だ。だからこそ、この曲は、聴く人それぞれの片思いの記憶と重なり、いつまでも胸の奥で淡く光り続ける。